今日はクラリネットパートのNが担当します。
始まりの合図
5月祭も終わり、先日からサマコンの練習が始まりました‼️練習初めの曲は今年のメイン曲である「チャイコフスキー交響曲第5番」。数十小節に及ぶクラリネット2本のユニゾンから始まります。つまり、サマコン期の練習は私たちクラリネットパートから始まったのです。チャイ5ではつねにクラリネットが重要な役割を果たす作品。これは僕がチャイ5という難曲に立ち向かうまでの記録である。
恥ずかしながら、僕はチャイ5は断片的にしか聞いたことがなくてチャイコフスキーはメロディが甘ったるく感じて勝手に敬遠さえしていました。しかし、せっかくサマコンでメイン2nd吹かせてもらえる機会をいただいたので向き合ってみるかーーって軽い気持ちで取り組み始めました。
練習方法
①音源をたくさん聞く
とにかくYoutubeに上がっている音源を聞き漁りました。チャイ5はいろいろな音源があって迷子になりそうです。嬉しい悲鳴😂
②スコアをみる
ここは誰がメロディを持っているか、どの和音がなっているかを一つ一つ確認していく。和音を頭の中で鳴らしながらスコアを見ていくと楽しくて夜も寝られませんね。楽典の知識も色々と出てきて面白いのですが、書き出すと止まらなそうなので割愛。説明上手な人に任せます!
③スコアをピアノで弾いてみる
実際に音を鳴らしてみないとどういう響きができるのか完全に掴みきれないので、スコアをピアノで弾いてみる。ホルンやヴィオラの音を読むのに悪戦苦闘😫慣れないピアノと戦いながら少しずつ進めることができました。実際に弾いてみると響きの移り変わりが割と素直だなーなんて思ったり。チャイコフスキーも根は誠実でピュアな人間なんだとしみじみ(会ったことはない)
④クラリネットでスケールをさらう
次にクラリネットの音色では響きがどうなるのか、スケールをやりながら調の持つ響きを確認していく。ピアノでの響きと全然違うじゃん‼️って思うことがありたまりませんね。余裕があればスコアに出できたコードのアルペジオもやれると楽しさ倍増👊使うのはもちろん、アイヒラーの「Scales for Clarinet」。クラリネット奏者のバイブルですね♪
⑤音源をまた聴いてみる
今度は色々と理論武装したので余裕やろと思って音源を聞いてみる。いや、ようわからん……(ノД`;)。ぶちのめされましたーー。音楽の懐の深さに感謝です。素直に練習しましょう。
⑥パート譜をさらう
やっとパート譜をさらっていく。メトロノームを曲のテンポよりずっと下げて設定して、できるようになったら少しずつ上げていきます。どんどん出来るようになる過程が成長を実感させてくれてうれしいです。ここまで来るとチャイコフスキーに心酔してますね❤️🔥
そんなこんなで初回練習が来てしまいました。冒頭のユニゾンは音程はピッタリ1stに付けられましたが、表現の面ではまだまだ改良の余地が残されてるなという印象。4楽章の速いパッセージはまだ完璧には程遠いですが、地道に練習してくらいついて行くぞ🤜
「神は細部に宿る」
ちょっと雑談……
「神は細部に宿る」
この言葉を誰が初めて言い出したかは定かではないが、細部までこだわることの重要性を説く言葉として誰しもが聞いたことがあるだろう。しかし、細部までこだわり抜くなんて並大抵の事ではない。チャイコフスキー第5番の譜面を前に途方に暮れていた。そんな時に図書館で一冊の本に出逢った。ヤン・スマッツ著「ホーリズムと進化」(1926)。部分の総和は全体を意味しない、部分の理解を積み重ねても全体を理解したことにはならない。スマッツは南アフリカの首相を2度務めるが彼の晩年からある意味で人類全体への理解を放棄した人種隔離政策が推し進められたのは残念なことである。もう一つ先人の言葉を拝借しよう。「神は固体を創造し、悪魔は表面を創作した」。物理学者パウリの言葉である。当たり前だが我々は表面しか知覚できない。テンポや音程といった表面的な事柄には気を配ることができるがそれで感動的な音楽を生み出すことができるのか。表面しか知覚できない悪魔の奴隷たる人間が神が創造した内面に迫ろうとする営みが音楽なのだろうか。
2023/5/20 上野・不忍池の端にて
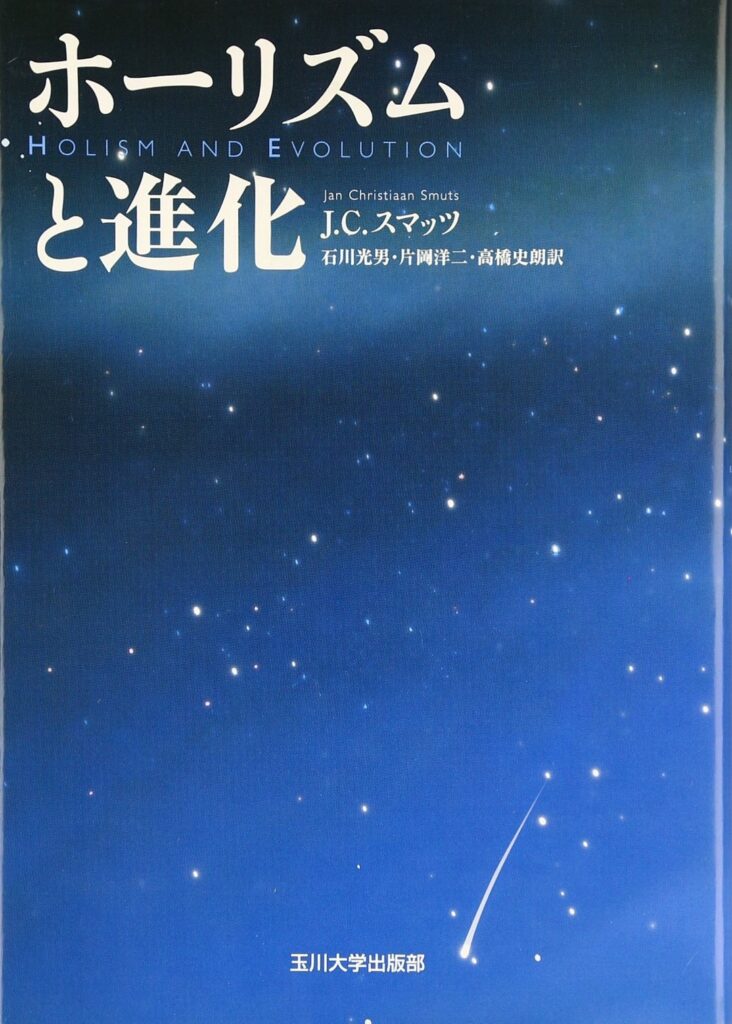





コメント